第1回 気象遭難に遭わないための天気講座
〜晩秋から冬の天気を知ろう〜
気象遭難に遭わないための天気の話をしたいと思いますが、実際に天気図を見て天気を予測するだけではなく、そういう天気になったときに、どんなリスクがあるのか、どういったことに気をつければいいのかを学んでいきたいと思います。私が今まで山で体験してきたこと、そして実際の天気図解説の大きく二本立てで、いきたいと思います。
そもそも、気象遭難とはひとことでいえば、気象が主たる原因で発生する遭難事故ということですよね。山では道迷いや転滑落など、いろんな原因があって事故が生じますが、そのなかで、主因が気象によるものを気象遭難という括りで言っています。
では、具体的な気象遭難にどんなものがあるかというと、落雷事故、熱中症、強風による転落滑落、強風によるテントの倒壊、大雨が原因で土砂災害、河川の増水、山だと沢で流された…。いろいろありますね。その中でも今回お話するのは「冬」に限定しまして、「冬における気象遭難」について考えてみたいと思います。
冬の寒さによって引き起こされる障害ですが、まずは凍傷がありますよね。凍傷というのは、じつはよほど厳しい気象状況だとか、標高7000mや8000mとか、そういうところに行かない限りはかなりの割合で防げます。それには、大きく3つあり、濡らさない、長時間同じ方向からの風を浴び続けない、肌をなるべく露出しないことが大切です。それと、手足の毛細血管には血流がいきにくくなるので、手足の感覚があるかどうかもチェックしながら動かすなど、そういった意識も重要かと思います。
次に低体温症。これはひどい場合には凍死へと結びつくのですが、経験上、だいたい3つのパターンがあると思います。一つめは純粋に悪天候によるもの。悪天候にもかかわらず、登山を決行したとか、悪天候になるという予測をできなかったとかいうことによって、厳しい気象状況に追い込まれたてしまうこと。二つめは、そこまで厳しい気象条件ではないのですが、長時間山中にいることで起きる場合。例えば滑落事故を起こした。すぐに救助してもらえればいいのですけど、救助するまでに時間がかかり、場合によっては一晩ビバークしなくてはいけないとか、そういうようなときに発症するケースです。三つめは疲労によるものです。例えばアプローチのラッセルが大変すぎて、自分の想像よりもはるかに体力を使い、山頂までに力を使い果たす。山頂に着いたとたんホッとして、そこから下れなくなってしまう。気持ちが張っているうちはなんとかなるのですけれど、それが「あー着いた。よかった。」って思ったときに、それまで使った体力の分、気力がガクンと落ちてしまいます。帰りのことまで考えて、自分の体力だとか計算しながら歩かないと、厳しい気象状況には打ち勝つことができません。
強風による転・滑落もありますよね。強風とひとことでいっても、実際に強い風が吹く場所と、そうでない場所がありますし、地形によっては想像をしていなかった方向から風が吹くこともあります。だから、山での風は、実際にそこに立ってみて、どの方向から、どんな風が吹いてくるのか、そういうのを意識するのが大切です。とくに注意したいのが、富士山など、単独峰での風下側での風。風下側では風上よりも風が弱いのでは…と思うかもしれません。確かに、風上は風下よりも風は強いのですが、おおまかな特徴として一定方向から吹きます。なので、対策しやすいのですね。ところが風下は、ひとつの目安として風上に比べて風速は3割減にはなるのですが、吹き返しの風が吹き、場合によってはつむじ風のような巻き上がる風が発生することもあり、風速だけではくくることができない、風による遭難が生じることがあるのです。直接的に気象現象とは関わりが少ないかもしれませんが、雪崩や雪庇の踏み抜き、凍結による事故などもあります。
いくつかのケースを紹介しましたが、それが実際にどういう時に発生するかといえば、予想していなかった気象状況が起きたとき、状況が急激に変化したとき、予想以上の厳しい状況、想定を超えるシビアな気象状況になったとき、こういうときは気象遭難が発生するケースがみられることが多いようです。
今はヤマテンさんだとか山の予報を専門に出してくれるところがあり、すばらしい予報を出して、気象遭難防止にも役立っているかと思いますが、注意したいのは、あくまでも予報は予報。それを生かし、自分で判断する、そういう力を持つことが重要です。これは山の予報に限らず気象庁で出す予報もそうですが、自信を持って出す予報と、例えば雷注意報など、夏場はほぼ毎日出ている念のために出す予報もあり、本当に危険な雷注意報なのか、それともちょっと注意してくださいという雷注意報なのか、自分でちゃんと判断できるくらいの力が必要だと思います。
■気象遭難とはなにか
■天気図の読み方
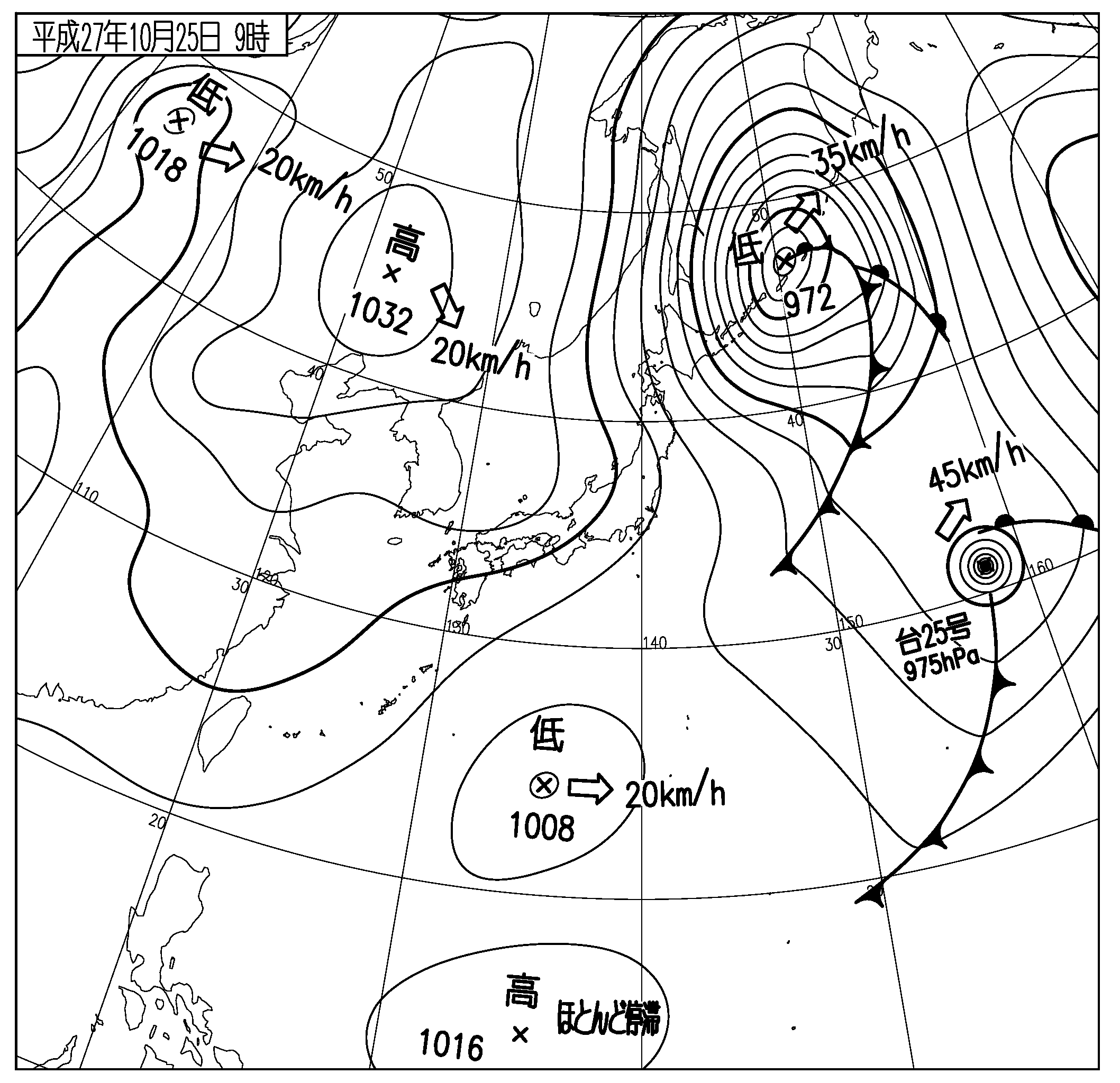 図1 |
|---|
 図2 |
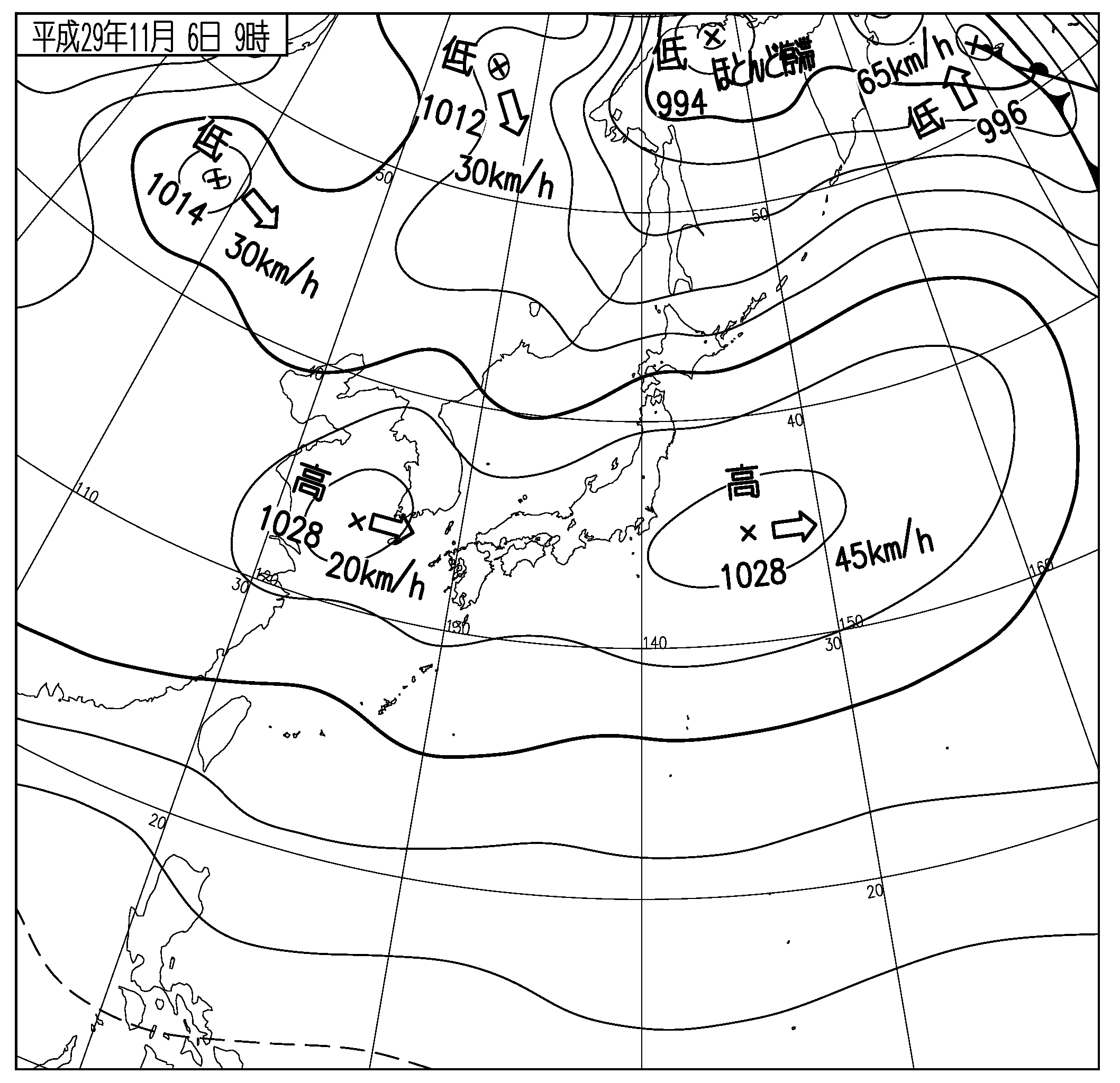 図3 |
ここからは実際の天気図をもとに考えていきたいと思います。まずは、移動性高気圧についてです。移動性高気圧は春や秋によく見られ、西から東へ周期的に移動してくる高気圧のことです。晴れの天気をねらうには、この高気圧に日本付近が覆われているときをねらうとよいのです。注意したいのは、移動性高気圧には暖かい高気圧と冷たい高気圧の2種類があるということです。
冷たい高気圧というのは寒気を伴った高気圧(図1)で、シベリア方面から張り出してくるタイプ。こうした高気圧でも日本に接近してくると天気はよくなるのですが、接近してくる最中、平地ではだんだん晴れる一方、山ではむしろ天気がわるくなることが多い。この時の上空500hPaのときの高層天気図(図2)を見ると、北のほうから南に等高度線が凸になっている。こういうのを気圧の谷と言いますが、要は北から冷たい空気が南下してきていると気象学的にはとらえます。地上の天気図だけを見ると、別に低気圧でもなんでもないのにと思うかもしれませんが、じつはその上空には寒気が流入しているため、高いところには雲が発生しやすく山の稜線では天気がわるい、ということが生じるのです。
一方で、暖かい高気圧とは、北のほうからではなくて、西または南から日本列島にやってくる場合の高気圧が相当します(図3)。この高気圧は暖かい空気を伴っていることが多く、この時の500hPa高層天気図(図4)には明確な気圧の谷や尾根はないですよね。こんな高気圧であれば、早くから天気がよくなり、山の上もそんなに寒くはならないということになります。
以上をふまえて、実践講習として、今日午前9時の天気図(図5。HBCのもので統一したい)を見てみることにします。日本列島の東には前線を伴った低気圧がありますが、大陸北部から高気圧が南に張り出してきているので、これはもう冷たい高気圧だということがわかりますよね。改めて高層天気図(図6)を確認してみると、日本列島の西には気圧の谷があり、日本海の上空では寒気が流入しています。ところが、海水温の高い日本海がある下層では当然暖かく湿った空気があるので、対流が活発となり、結果、雷が発生しやすくなります。さっき、会場の外でゴロゴロっときたのはまさにそれですね。
こちらは明日午前9時の予想天気図(図7)です。日本海にあった低気圧は消え、大陸から高気圧が張り出しています。この天気図だけを見たら、これはいいぞ、明日は晴れだと思う方は多いと思います。ここでも、高層天気図(図8)を見るのがポイントになります。日本列島上空には深い気圧の谷があります。これは強い寒気が流入していることを示しています。このことから地上天気図に描かれている高気圧は、上空に寒気を伴ったいわゆる冷たい高気圧であることが分かります。さらに渦度に注目してみると、周囲より数値が高くなっています。日本海側の地域や北陸では雲が非常に発生しやすい状況にあるのです。このように、地上天気図だけではなかなか正確に天気を予測することはできません。
 図4 | 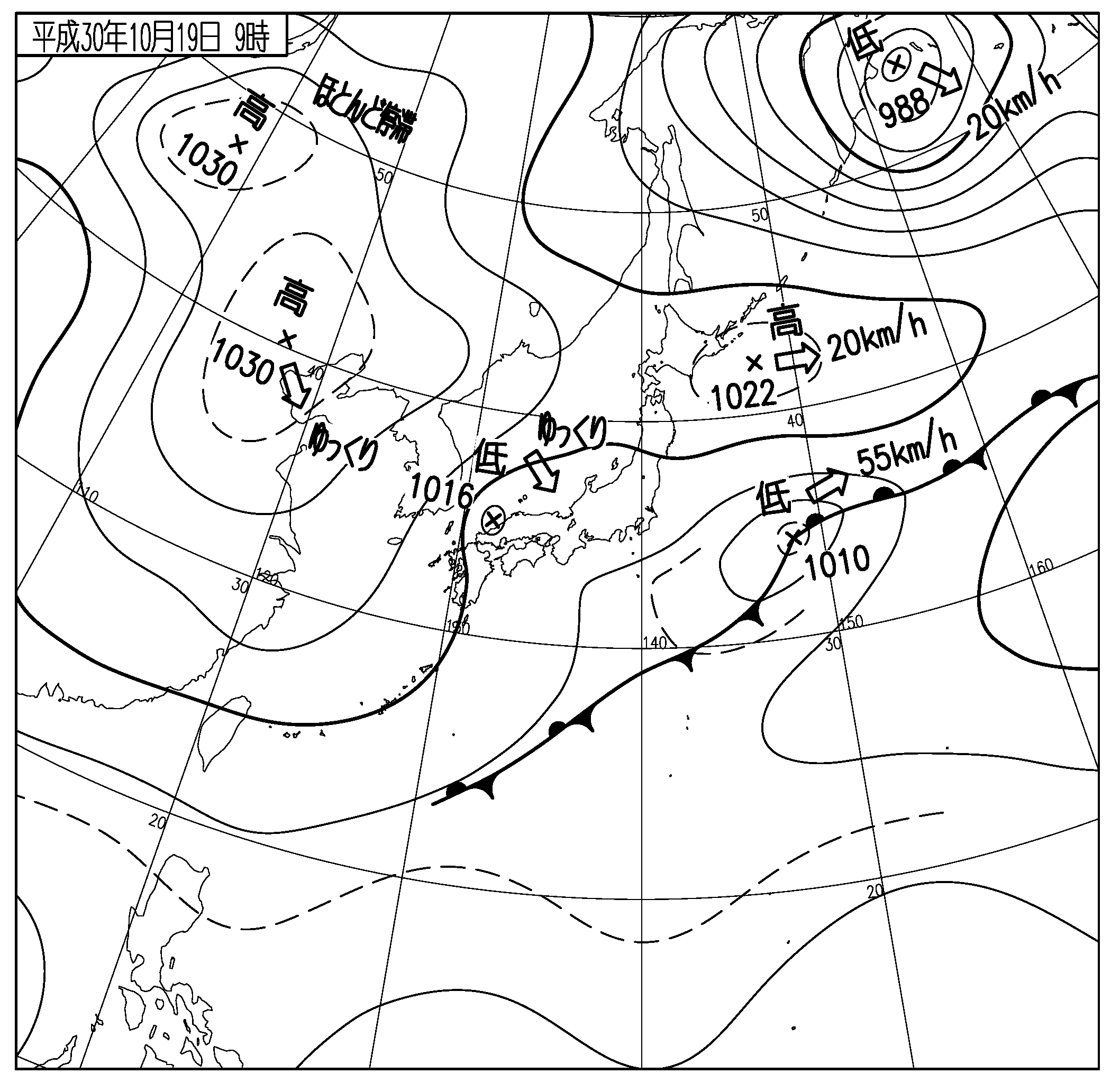 図5 |  図6 |
|---|---|---|
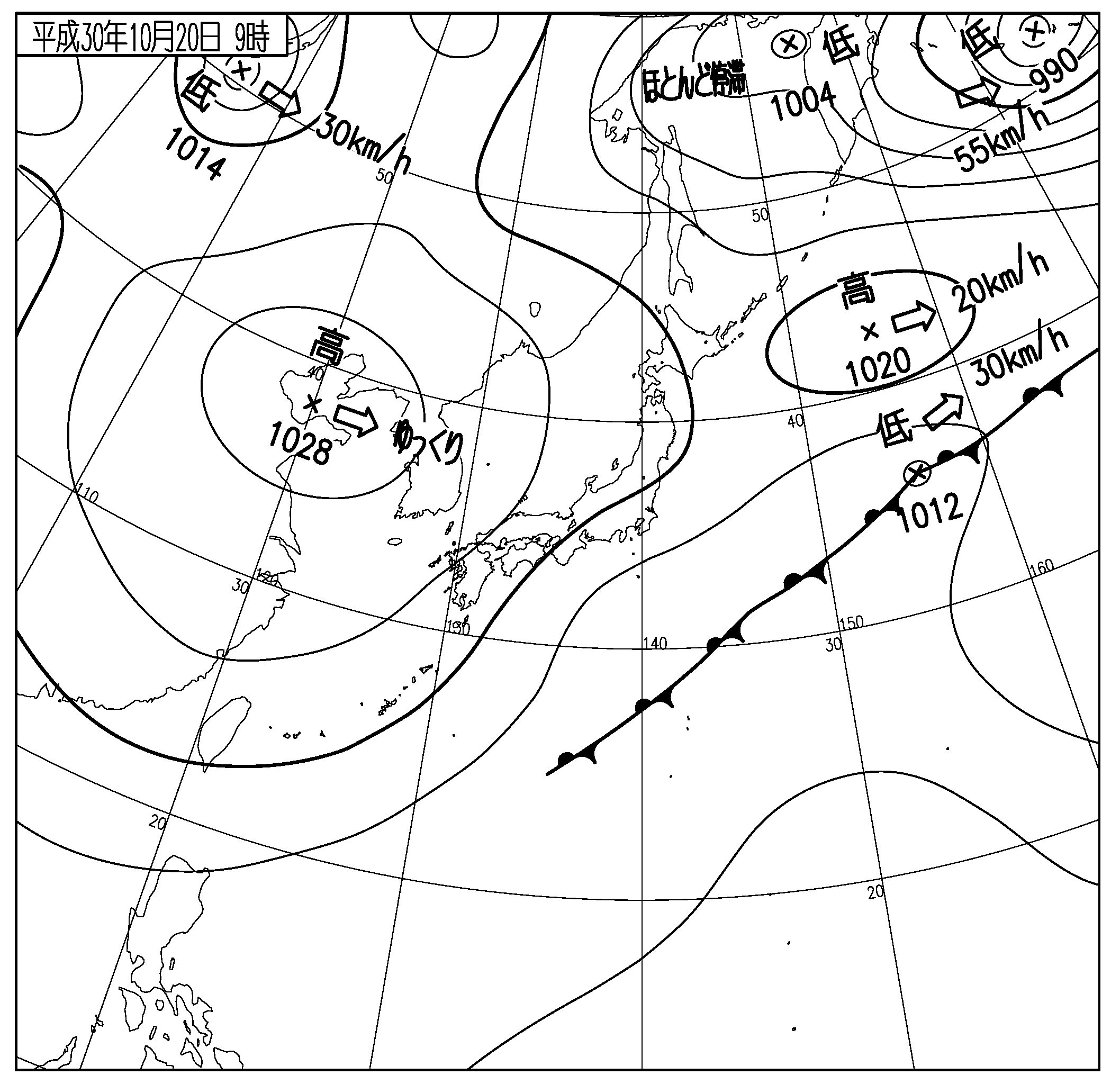 図7 |  図8 |
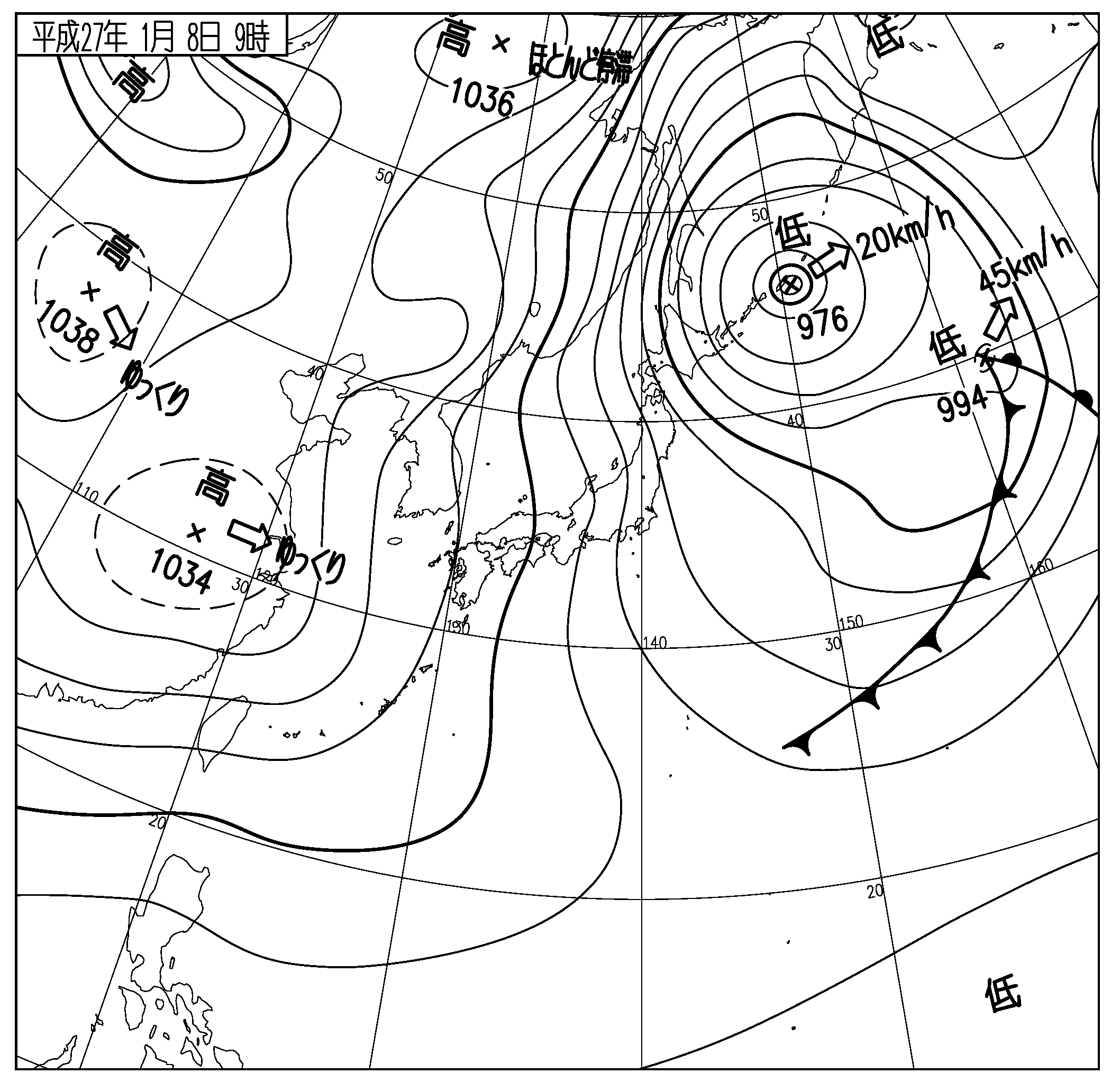 図9 |
|---|
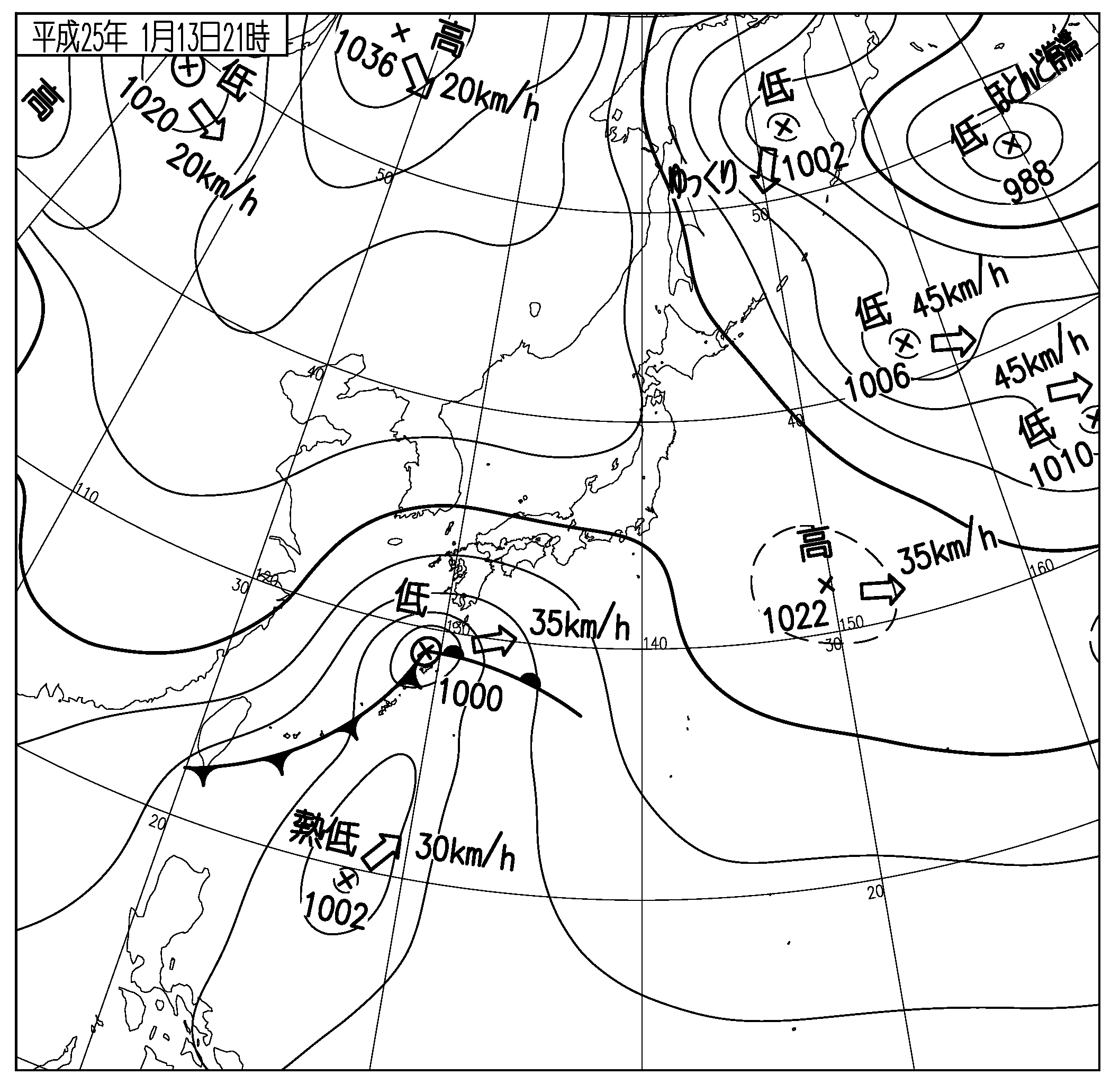 図10 |
 図11 |
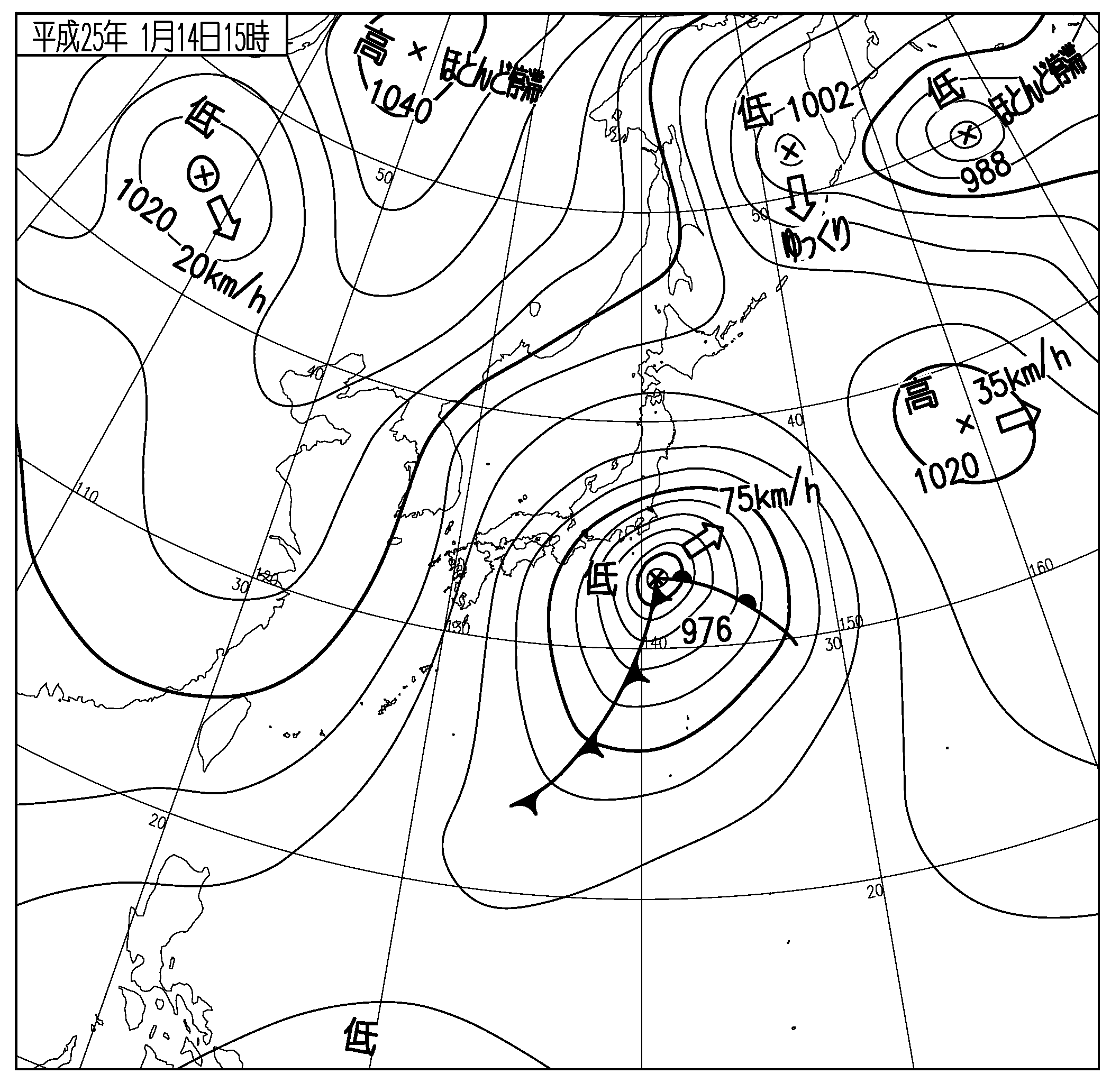 図12 |
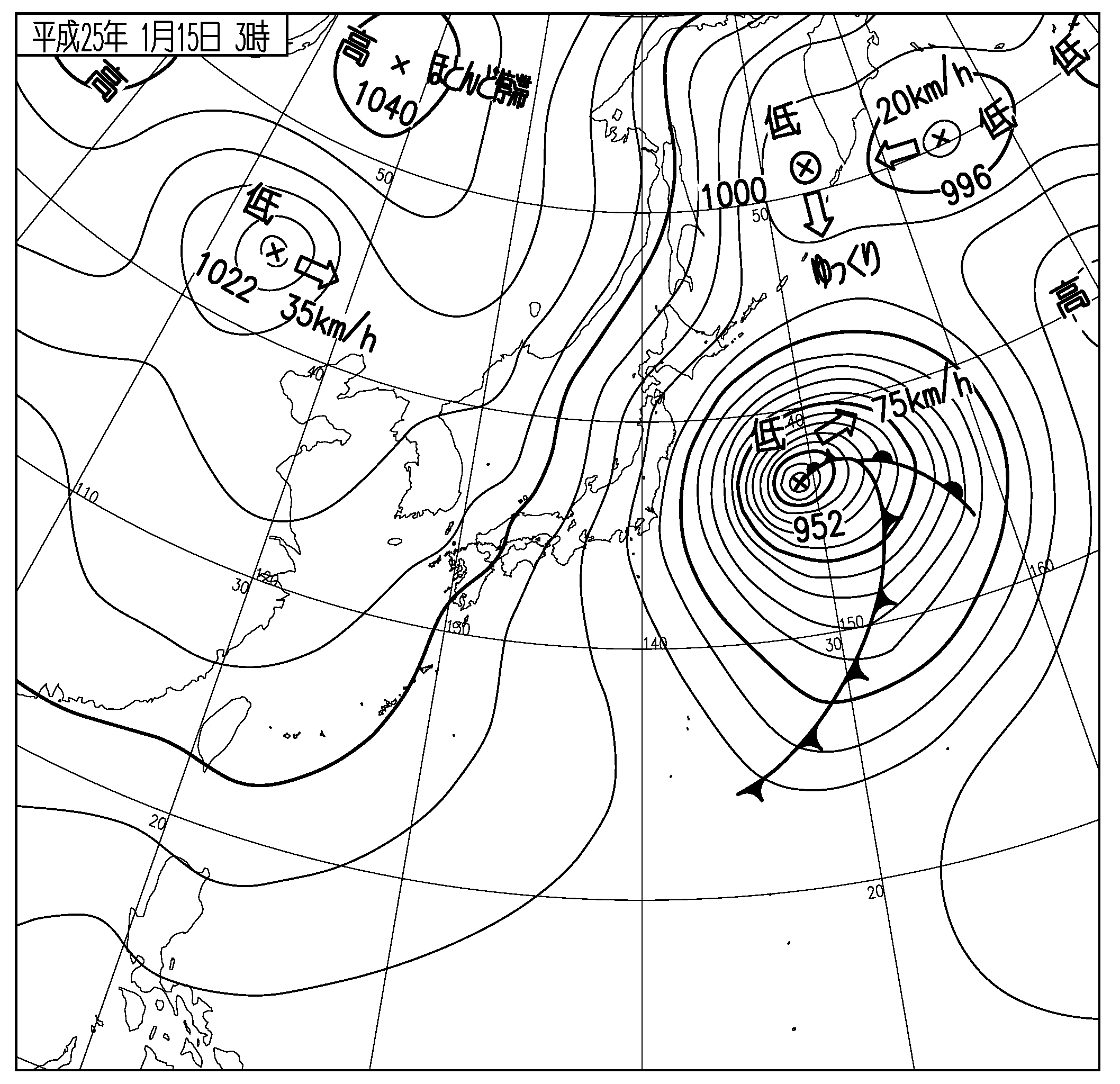 図13 |
冬の代表的な天気図といえば、西高東低の冬型の気圧配置(図9)です。日本列島に対し、日本列島の西に高気圧、東に低気圧があるパターンです。この天気図の特徴は、シベリアからの寒気が日本列島に流れ込み、日本海側は雪、太平洋側は晴れて乾燥することです。天気図を見る際のポイントは、等圧線が縦縞になるということ、寒気の流入度合は等圧線の間隔が狭くなるほど強くなるということです。気圧の高いところから低いところへ風が吹くのであれば、西風になるのでは? とみなさんは思うかもしれません。これには地球の自転効果が影響しており、風は高気圧では右回りに吹き出し、低気圧では左回りに吹き込みます。結果、西高東低の場合は等圧線に沿うように、日本列島に北風が吹き込んでくるのです。
この北風によってシベリアから来る非常に冷たい風が、日本海上を吹き抜けて日本列島にやってきます。日本海は暖かい対馬海流が流れ込んでいるため、世界的にみて、緯度のわりに海面水温が非常に高いのが特徴です。この状況を例えていえば、冬の露天風呂です。冬の露天風呂ではもうもうと湯気が立ちますよね。これとまったく同じ状態が冬の日本海では生じるのです。この〝湯気〟が雪雲、冬の積乱雲です。北風に乗って日本列島に流れ込んだ雲は、日本海側の地方に雪を降らせ、更に日本を背骨のように縦断する山脈(脊梁山脈)にぶつかって、強制的に上昇させられます。この上昇によって雪雲は北アルプス等の山々に更に大量の雪を降らせまるのです。
雪を降らせた後はどうなるか。山脈を越えた風は斜面に沿って、今度は下降気流になります。標高の低いところの気温は高いので、雲は消えていきます。このため、北アルプスの風下側にある松本平は、冬に晴れることが多くなります。この北風はさらに美ヶ原、八ヶ岳に向かって吹きます。この先は、もうおわかりですよね。再び上昇気流となり、同じ仕組みで山に雪を降らせます。ただ、一度雪を降らせた後の空気なので、水分量はだいぶ減少しており、降雪量は少なくなります。さらにその風は関東平野へと吹き出していき、その時はもうからっから。だから、冬の太平洋側は非常に乾燥するのです。
では、松本市より北にある長野市ではどうでしょう。長野市では、日本海側ほどの降雪量はないにせよ、冬は曇天が多いですよね。これはそれぞれの北西側にある山脈が主因になっています。松本市の北西側には北アルプスがある。長野市の北西にはそこまで高い山がなく、上越につながる谷があるため、日本海から雪雲が流れ込んでしまう。さて、同じ論理で太平洋側にも雪が降りやすい都市があります。どこかわかりますか。答えは名古屋です。名古屋の西には関ヶ原、琵琶湖があり、地形的に低くなっており、雲の通り道ができています。このため、太平洋側であっても度々雪が降るのです。
次に南岸低気圧(図10〜13)があります。南岸低気圧とは日本列島の南岸を発達しながら東進する低気圧です。関東地方に雪を降らせるのはこの低気圧です。低気圧からの距離や発達の度合い等によっては、日本海側ではそれほど大きな影響はでないこともしばしばです。この天気図の場合の東京では、大雪となり、その後、1002hPaだった低気圧は996、976、952hPaと猛烈に発達し、最終的には西高東低の冬型の気圧配置となりました。南岸低気圧は、富士山や南アルプスでたくさん雪を降らせ、この事例の場合は通過後に西高東低となり、北アルプスでも降雪となりました。
八ヶ岳は日本海側と太平洋側の間にあるため、強い冬型の場合はそれなりの降雪がありますし、南岸低気圧の場合に大雪となることもあります。低気圧の進路や発達の度合い、寒気の流入、気圧配置などにより、天気は変わりますから、みなさんも調べてみてください。
最後に紹介するのは日本海低気圧(図14〜17)。発達しながら日本海を東北東あるいは北東へと進む低気圧です。この低気圧は強い南風により気温が上昇した後、寒冷前線が通過して気温が急降下するのが特徴です。山では多くの気象遭難を引き起こしており、注意すべき低気圧です。春一番はこの低気圧によってもたらされる南風です。
まずは天気図を見て、日本列島にどのような影響が出そうか判断できるようになることが第一です。そのうえで、今度は自分がいる場所、もしくはこれから行こうとする場所ではどんな気象状況になりそうか想定しなければなりません。想定する気象状況の中で、発生する可能性のあるリスクは何なのか。これをイメージし、リスクに備えるのが、天気図を読む重要なポイントとなります。
■覚えておきたい冬の天気図
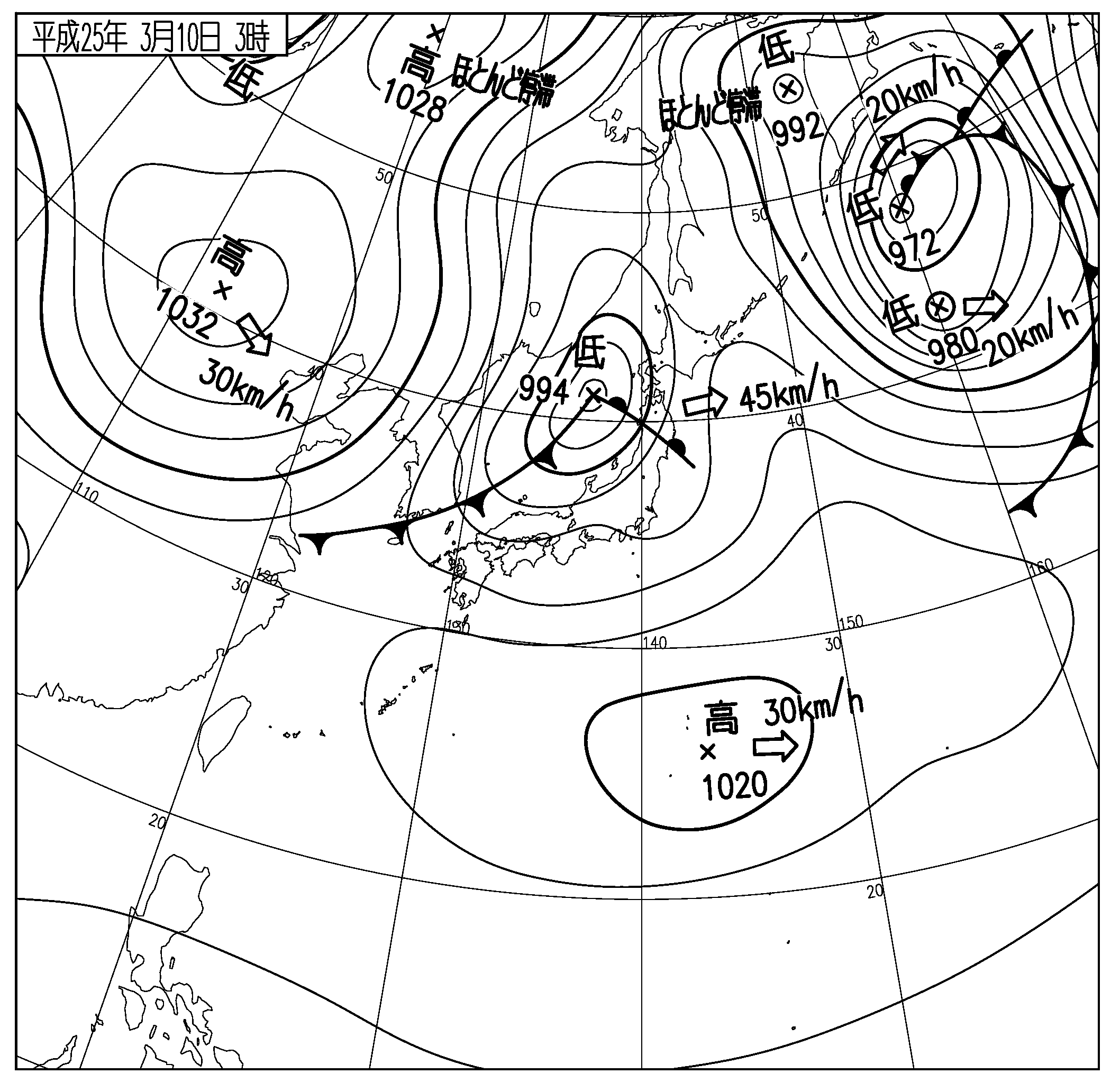 図14 | 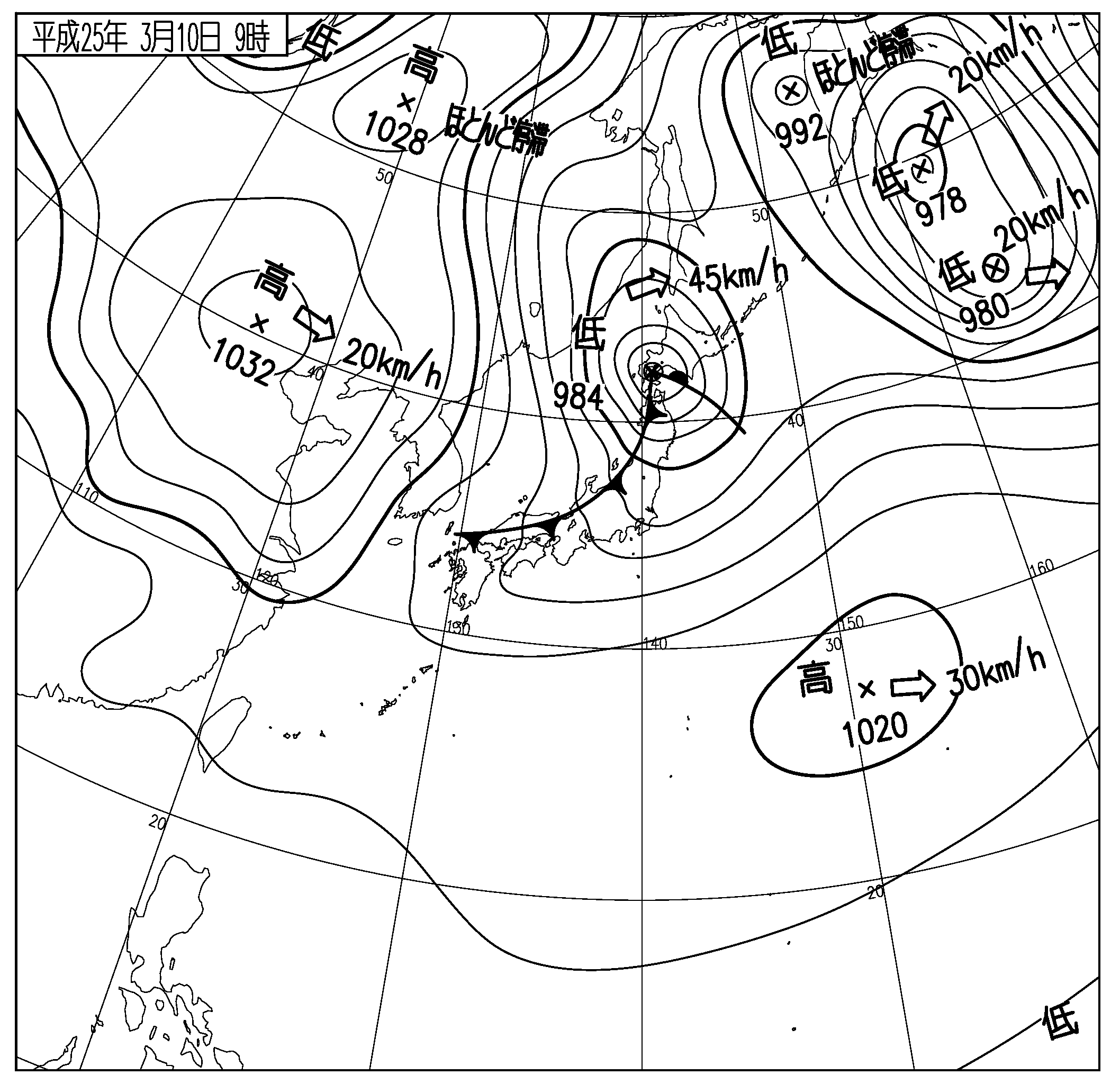 図15 |
|---|---|
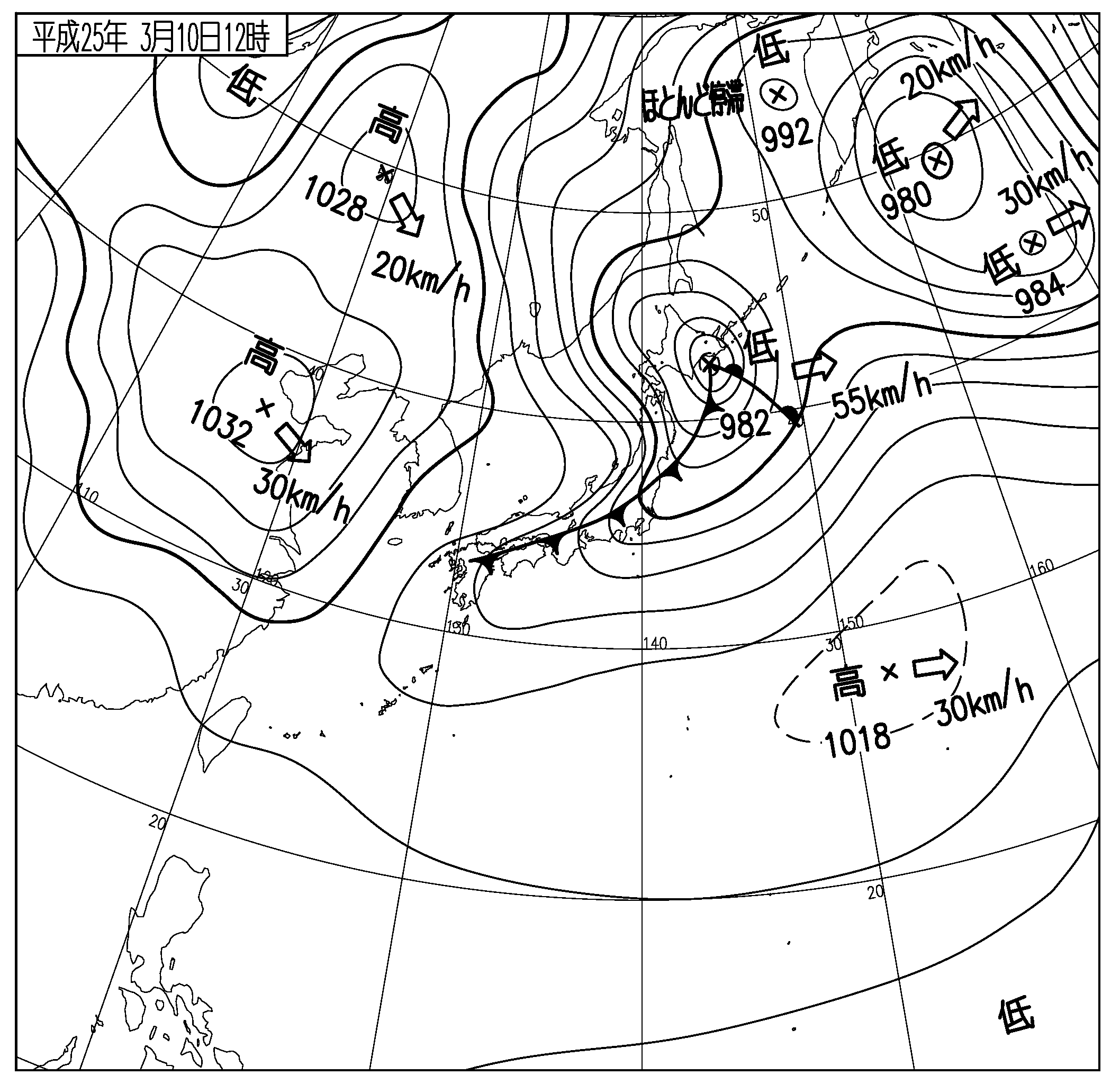 図16 | 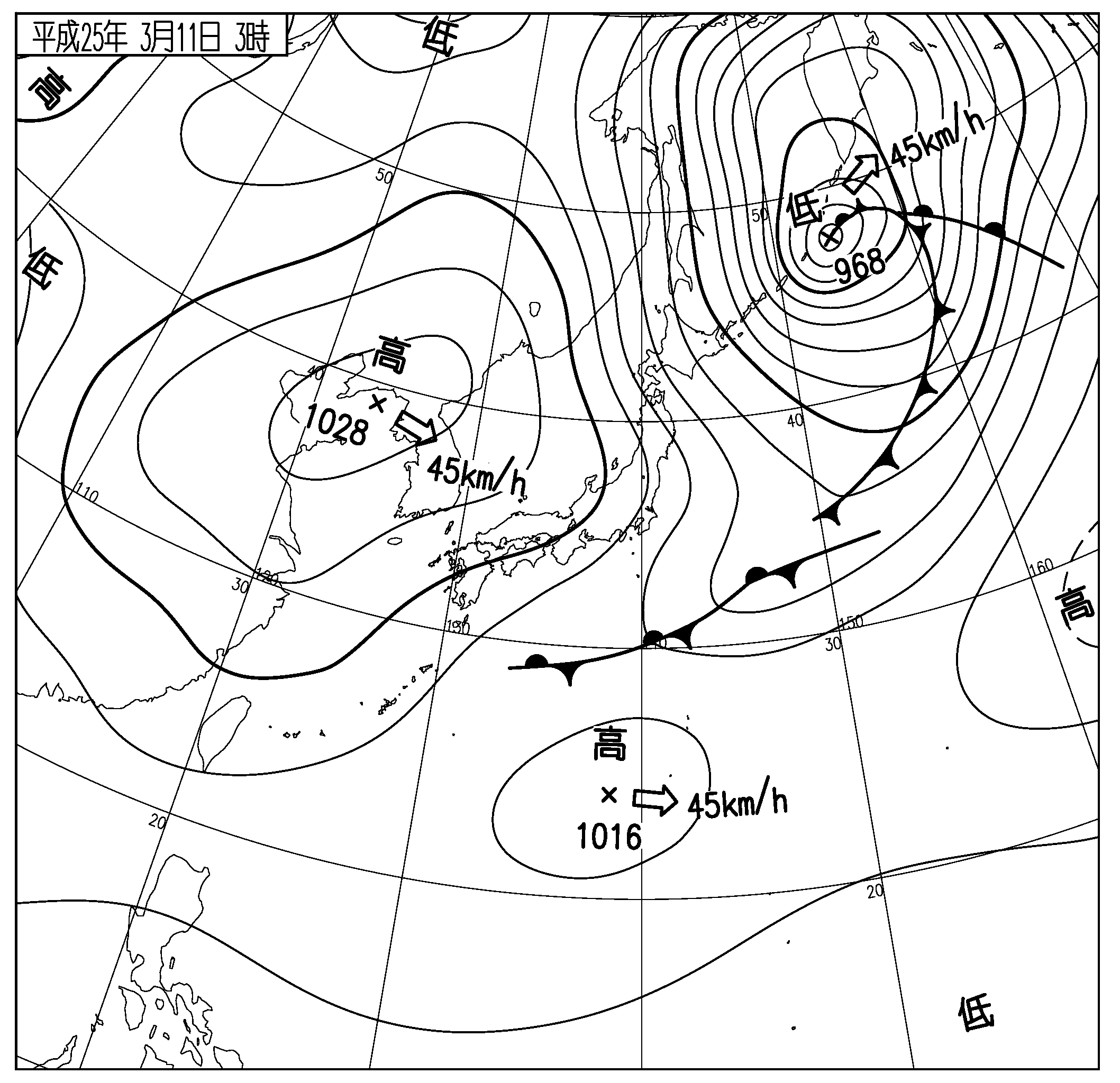 図17 |
■もしも気象遭難に遭遇したら
最後にお話ししたいのは「もしも気象遭難に遭遇してしまったら」ということです。準備をし、対策をした。けれど、遭難してしまった。登るのは人間ですから、時にそんなこともあるでしょう。そんな時は、まずは冷静になることです。これは数年前、西穂で起きた実例ですが、ご夫婦で登られた方が独標から下山してくるときに遭難された。最初滑落したのは奥さんのほうでしたが、それをみたダンナさんは奥さんを助けようと谷へ下りて行ってしまった…。通報したのは奥さんの方でしたが、こんな時、ダンナさんはどうすればよかったのでしょうか。
目の前で奥さんが滑落すれば、自分が何とかしようって助けに行きたくなる思いは当たり前で、それは決して責められることではありません。ですが、実際には何をしなければいけなかったかというと、山小屋なり警察なりに自分から電話をかけることだったと思います。もしその時に、ダンナさんが救助要請をしていれば、山小屋が受けようが警察が受けようが、「まずそこにいてください」と言ったはずです。その時にまずは何をしなければならないのか、救助を心得ているものなら、的確な助言をくれます。当日は猛吹雪でホワイトアウトの状態。救助隊が駆け付けた時に、場所が特定できていれば、すぐ救助活動に入れるわけです。しかし、どこにいるのか分からないとなれば、救助活動ではなく捜索活動から入らなければならなくなります。これは大変大きな違いで、助かるか助からないかの分岐点になる可能性も大きいのです。事故が起こったら、人間普通の精神状態ではいられないのは当然です。だからこそ、警察でも、山仲間のベテランの人にでもいいので、電話一本、何をすべきか助言を仰ぐことです。話すことによって自分が冷静になれるという効果もあります。大切なのは、自分が冷静になって初めて、今できるベストな方法は何なのかというのが見えてくることです。最初のアクションは非常に重要なので、まずは一報、しっかりと頭に入れておきましょう。
それともう一点。もし、自分自身が滑落など、遭難の主体者となったとき。その時にいちばん大事なことは、絶対にあきらめないということです。人間、山に限らずいろんな場面でも窮地に陥る。これは助からない、そこに道がないと思う瞬間があるかもしれないけれど、でもそこで「ない」って思ったら本当に道はなくなってしまいます。道がないと一瞬思ったとしても、もがいて、なんとかしようとする。そこで、奇跡的にスーッと細い道が一本開けるってじつはけっこうあります。この人は、あきらめたら絶対助からなかった、生きようとする一念があったからこそ生き延びた、そんな事例をたくさん見てきました。大変なことが起きた瞬間に、強い気持ちを発揮するというのは非常に難しいことだと思います。だからこそ、日頃からそういう気持ちをみなさんにもぜひ持っていただきたいと思っています。
滑落した事故を起こした瞬間に、意識を失う人は多いといいます。「あ、やってしまった」「あー、もうダメだ」…。でも、意識を失えば、人間、頭が重いので、絶対頭を下にして落ちていきます。そうなると、まず助からないですよね。でも過去にあった事例でも、落ちていくときに自分が落ちていくところ見ながら落ちていく、目を見開いて。次にあの岩に当たる、頭を打ってはいけないから、頭を守る。「あの岩を蹴るんだ」で、蹴った。次に落ちてって、「あそこに当たりそうだ」じゃあそれを蹴る、って400m落ちて助かった人がいます。その人は、足は折れていましたが意識はあって、自力で救助を要請をし、救助のヘリが来た時に鏡で自分の位置を照らして教え、奇跡的に助かりました。
もしものときには、まずは冷静になること。そして最後まであきらめないこと。それが生還につながるものだと思います。今日はどうもありがとうございました。
*2018年10月19日、松本Mウィング3-2にて収録